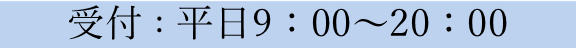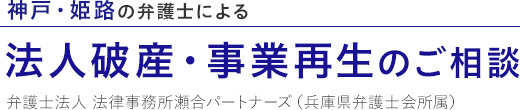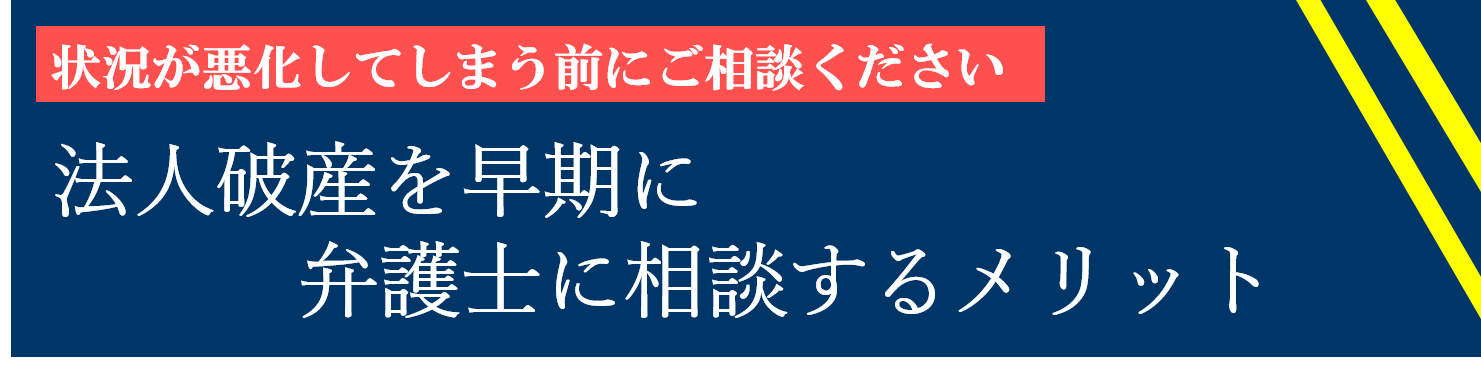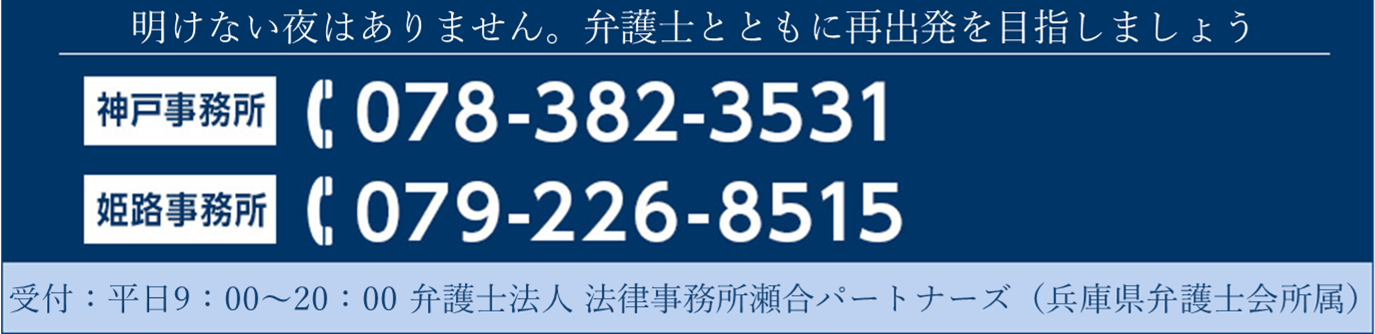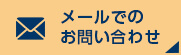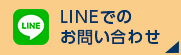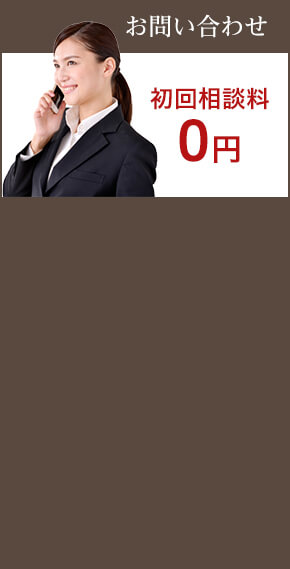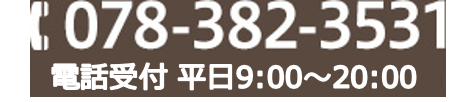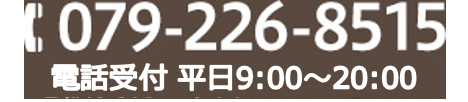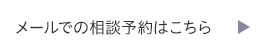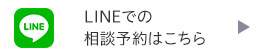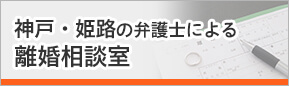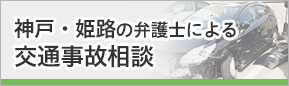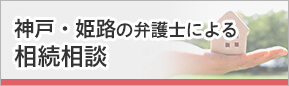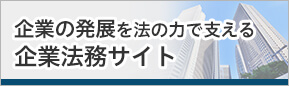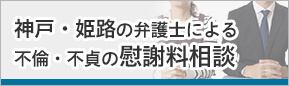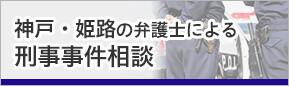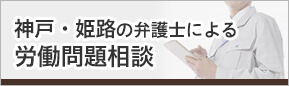病院が破産・倒産する場合の問題点と手続きのポイントを弁護士が解説
目次
はじめに
病院や診療所は社会的インフラの一部として重要な役割を果たしています。しかし、経営難などの理由で破産せざるを得ない場合、その影響は患者や従業員、地域医療に及びます。本記事では、病院や診療所が破産する際の特徴や手続きの流れ、通常の企業の破産手続きとの違いについて解説します。
1. 誰が破産をするのか
「病院」という名称自体は法的な主体ではありません。医療法第1条の5によると、
•病院:医師または歯科医師が公衆や特定多数人のために医業を行う場所で、20人以上の患者を入院させる施設を持つもの。
•診療所:19人以下の患者を入院させる施設、または入院施設がないもの。
病院の倒産とは、運営者の破産を意味します。具体的には、
•個人運営の病院 → 運営する個人が破産申立を行う。
•医療法人運営の病院 → 医療法人が破産手続きを行う。
2. 病院の破産手続きの特徴、留意点
□患者をどうするか
病院・診療所が破産する場合、最大の問題は入院患者や通院患者の安全確保です。裁判所、行政機関、地域の医師会と連携し、以下の対応が必要です。
•入院・通院患者の転院・転医先を確保する。
•転院に必要な期間や費用を把握する。
•生命・身体に危険がある患者については、早急に都道府県の環境保健部や保健所と協議する。
□従業員について
病院・診療所の破産手続きでは、通常の企業破産とは異なり、破産管財人だけでは管理が困難です。そのため、事務員や看護師の中から補助者を確保し、破産申立前に選定することが求められます。
•破産手続き開始後、破産管財人が財産管理を行う。
•看護師・事務員代表を補助者として選定し、雇用を継続する必要がある。
□診療録等の保管場所
医師法・医療法により、以下の保管義務が定められています。
•診療録(カルテ):診療終了日から5年間
•病院日誌・診療日誌・処方箋・手術記録・看護記録・検査記録・X線写真:2年間
破産後も保管義務は継続するため、以下のような対応が必要です。
•病院施設の買受人がそのまま病院として運営する場合、診療録等を引き継ぐ。
•買受人がいない場合、破産財団から費用を出して外部保管業者へ委託する。
□廃止届の提出時期
病院の廃止届を提出するタイミングは慎重に検討する必要があります。
•廃止届を出す前に、買受人が病院開設許可を取得しているか確認する。
•廃止届の提出が早すぎると、その地域の基準病床数に空きが生じ、新規病院が開設される可能性がある。
•結果として、買受人が病院を再開できなくなるリスクがある。
3. 病院の破産の手続きの流れ
病院の破産手続きは、以下の流れで進められます。
1.破産の検討と弁護士への相談
2.患者の転院・転医手続き
3.破産申立書の作成と提出
4.破産管財人の選任と財産調査
5.従業員の処遇決定
6.診療録等の保管対応
7.病院施設の処分または買受人の選定
8.廃止届の提出
4. 病院の破産・倒産を弁護士に相談する必要性
病院の破産は、患者・従業員・行政機関との調整が不可欠であり、専門的な対応が求められます。弁護士に相談することで、
•適切な破産手続きの選択
•債務整理や再生の可能性の検討
•法的リスクの回避
•患者・従業員への適切な対応 が可能となります。
5. まとめ
病院の破産は、患者、従業員、地域医療に多大な影響を及ぼします。そのため、
•破産という手段を選ぶ前に、再建の可能性を検討する。
•破産する場合は、転院・転職先の確保や診療録の保管を慎重に進める。
•破産手続きに詳しい弁護士と早めに相談し、適切な対応を取る。
病院の破産手続きについて疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。